──「届かない」理由とこれからの可能性を探る

世界じゃバッド・バニーとか鬼バズってるのに…

音、文化、メディア――いろんな壁があってさ。
今日はそのへん、ガッツリ解説してやるよ🔥
世界で躍動するレゲトン、日本ではなぜ…
Spotify年間再生ランキング常連、YouTube再生数数十億回、コーチェラでもヘッドライナーに──
レゲトンは今や世界のポップミュージックの中心の一つといっても過言ではない。Bad Bunny、Karol G、J Balvinらが築いた新時代のサウンドは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアでも支持を広げている。
…が、日本だけは例外だ。
クラブシーンや一部のラテン音楽ファンの間では確かにレゲトンは知られているが、一般層にはほとんど浸透していない。K-POPのような大衆化とは無縁のまま、「名前は聞いたことあるけど何かよく分からない」ジャンルになっているのが現状だ。
この記事では、なぜ日本ではレゲトンが流行らなかったのかを、3つの視点から深掘りしていく。そして、どうすればレゲトンが日本に届くのか? その可能性も探ってみたい。
メディアに取り上げられない音楽は「存在しない」のと同じ
日本のテレビ・雑誌・ラジオにレゲトンは“いなかった”
レゲトンが本格的に世界に出ていったのは2000年代中盤以降。Daddy Yankeeの「Gasolina」やDon Omarの「Danza Kuduro」が欧米でヒットし、2010年代にはJ BalvinやMalumaが世界的な人気を確立した。
しかし、このムーブメントは日本のメディアを素通りしてきた。
音楽番組では取り上げられず、雑誌や音楽評論でもスルー。
サマソニやフジロックなどの大型フェスにも呼ばれない
つまり、日本のリスナーが「出会う機会」そのものが極端に少なかった。流行るためには「まず耳に入る」必要があるが、それすらなかったのが現実だ。
一方でK-POPは…
K-POPが日本で広まった背景には、徹底したローカライズとメディア戦略があった。日本語バージョンの楽曲、地上波の音楽番組出演、握手会やファンミーティング。K-POPは「現場」と「翻訳」がセットで提供された。
対してレゲトンは、グローバル戦略の中で“日本語圏”を完全に後回しにしてきた。メディアを通じた文脈付けが行われないまま、「よく分からないジャンル」として認知されずに終わってしまったのだ。
デンボウのビートは“同じに聞こえる”問題
音の違いに敏感な日本人リスナー
レゲトンの特徴は、あの独特なリズム──「デンボウ(Dembow)」にある。このリズムが中毒性の源であり、踊りやすさの秘密でもある。しかし、耳慣れない日本人にとっては「全部同じに聞こえる」という印象を持たれがちだ。
実際、J-POPのリスナーはメロディの展開やコード進行の変化に敏感で、「起承転結」や「サビで爆発する感じ」を好む傾向がある。レゲトンのようにワンパターンに聴こえるビートがループする構造は、退屈に感じられることも多い。
メロディ重視のJ-POPとの対比
たとえば、AimerやYOASOBIの楽曲を聴いている層からすれば、Bad BunnyやFeidの曲は「ずっとノリが一緒」に感じられるかもしれない。これは文化的なリズム感の違いであり、どちらが優れているかではない。
だが、ここに「ジャンルを理解する翻訳」がなければ、「レゲトン=単調で飽きる音楽」という誤解が解けることはない。
曲に“ノる”文化が根付いていない
音楽=聴くもの、レゲトン=踊るもの
レゲトンはダンスと密接に結びついた音楽だ。パーティーや路上、スタジアムやクラブで身体を動かすことを前提に作られている。歌詞の意味よりも、ノリやフィーリングが重視される。
一方、日本では音楽は「じっくり聴く」文化が中心。ライブでも手拍子、口ずさみ、涙、拍手…踊ることが「正解」とされていないケースがほとんどだ。
“ノってる人”が浮いてしまう現場
クラブ文化やストリートダンスが根付いているラテン圏では自然な動きも、日本では「恥ずかしい」「浮く」と感じられがち。踊る=“特別なこと”という感覚が、レゲトンの本質を受け入れにくくしている。
おわりに:レゲトンを「届かせる」ために必要なこと
レゲトンが日本で流行らなかった理由は、音楽そのものが悪かったからではない。
「翻訳されなかった」「届けられなかった」だけだ。
- メディアに出ない
- リズムの構造が解説されない
- 踊ることへの心理的ハードルが高い
この3つが重なって、「レゲトン=なんか分からないジャンル」として扱われてきた。
しかし今は、個人が発信できる時代。
Spotifyプレイリスト、Instagramリール、TikTokダンス、ブログでの解説…。
“翻訳者”や“紹介者”になれる人が増えれば、レゲトンは確実に広がっていく。
次のブームの火種は、あなたの耳と身体の中にあるかもしれない。

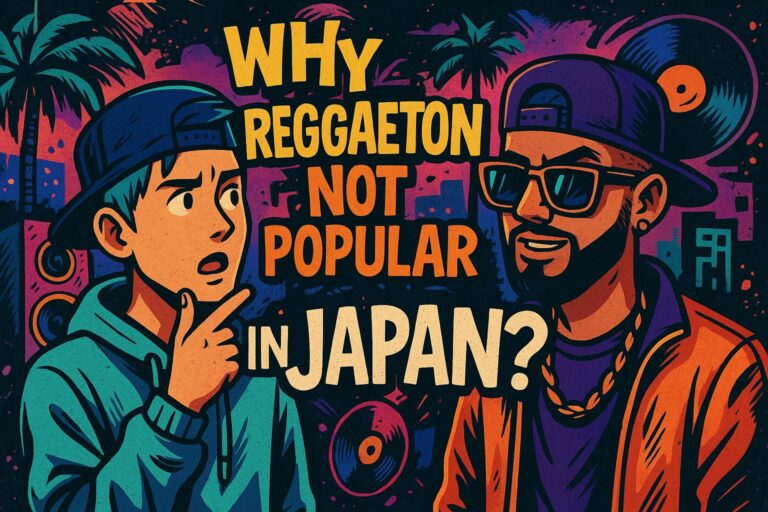






コメント